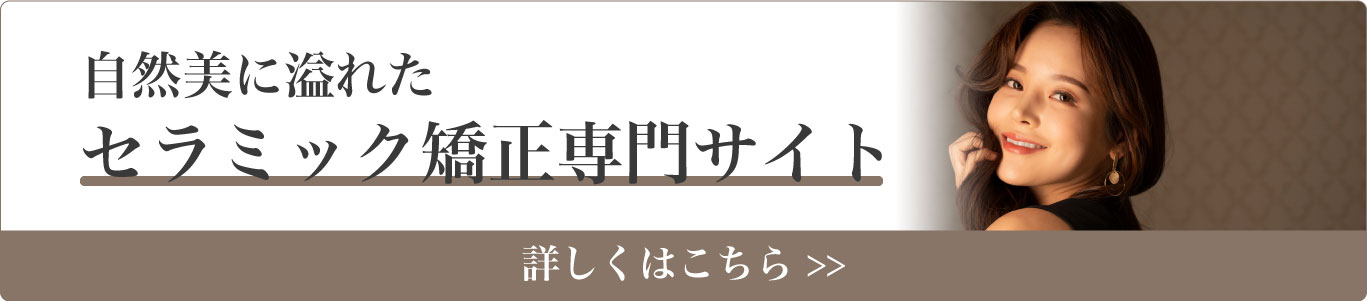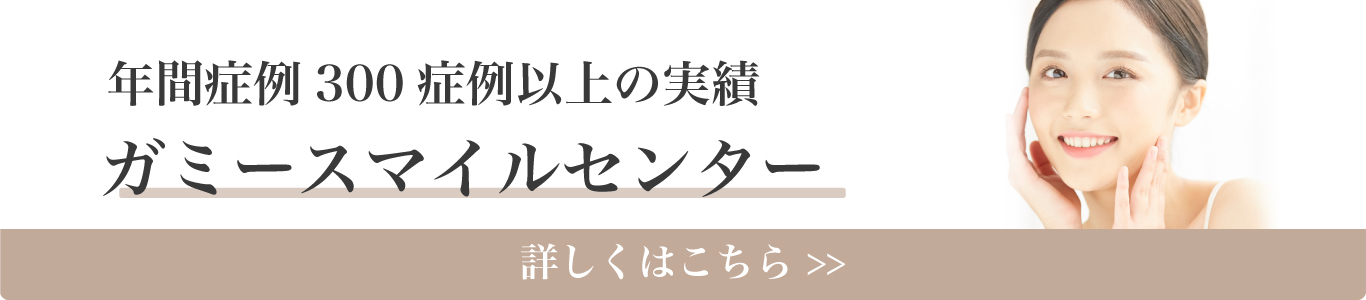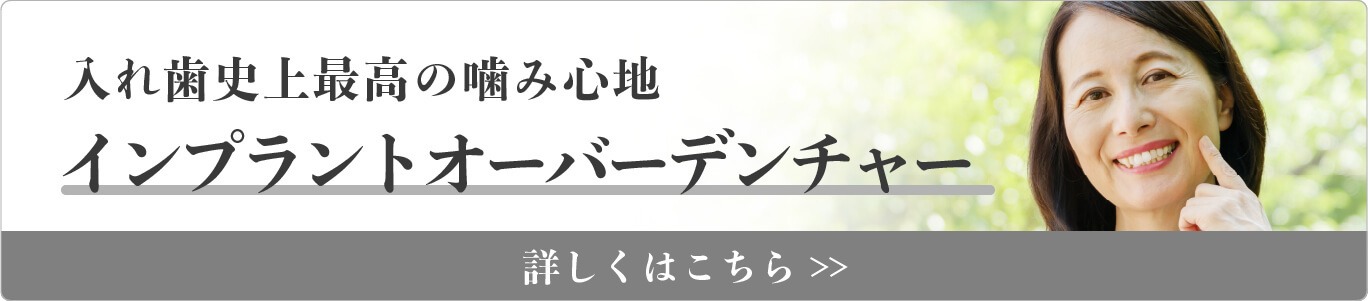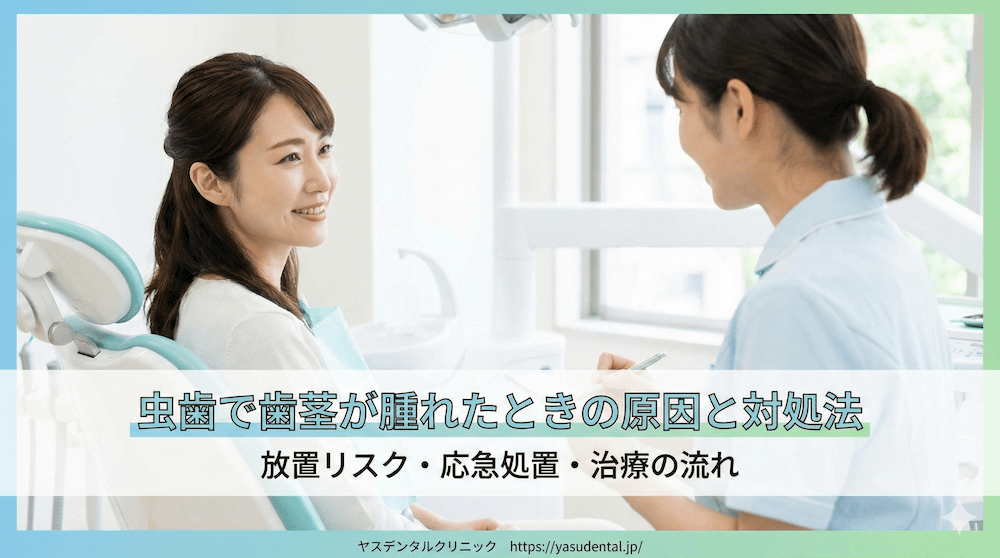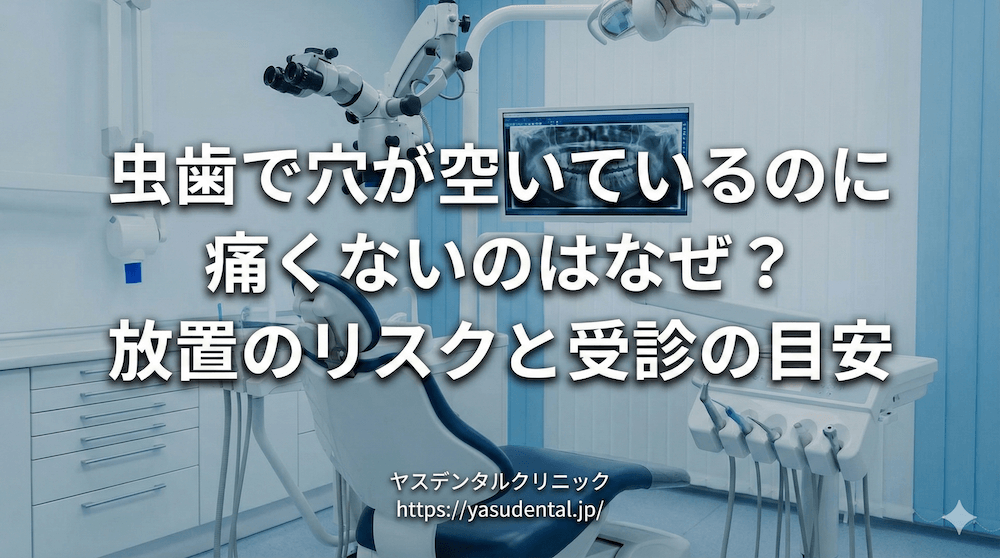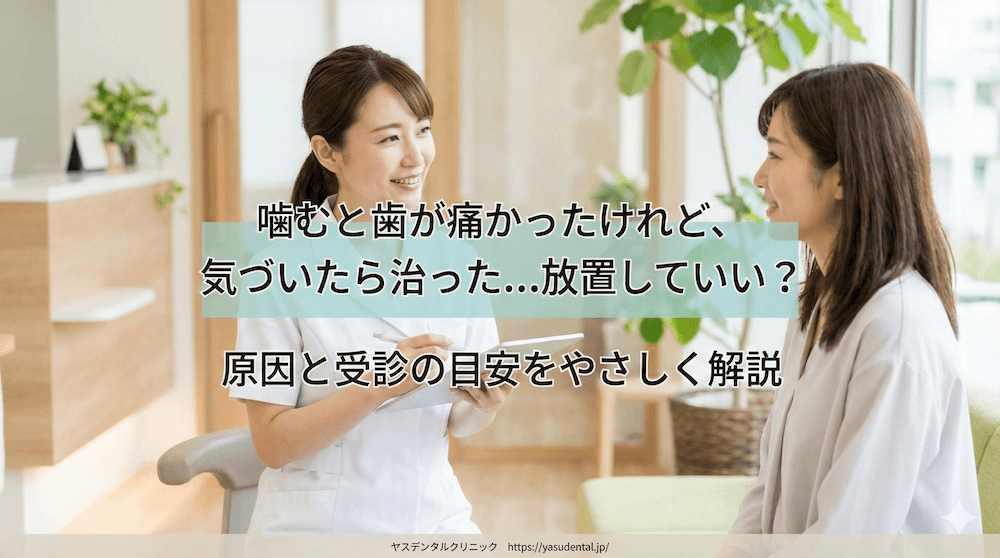プラークと歯石が引き金になる理由
歯の表面に付着するプラーク(歯垢)は、細菌が作る粘着性の膜=バイオフィルムです。この中で歯周病菌が繁殖すると、歯ぐきの炎症(歯肉炎)が起こり、出血や腫れが見られるようになります。
さらに、プラークが唾液中のカルシウム成分で硬くなったものが歯石です。歯石の表面はざらついており、細菌が再び付きやすくなります。これが炎症を慢性化させ、歯を支える骨にまで影響を及ぼすこともあります。
そのため、毎日の丁寧なブラッシングでプラークを減らし、定期的な歯石除去(スケーリング)を受けることが、歯周病予防の基本となります。
身体的な因子・環境的な因子が重なると進行しやすい
同じようにプラークがついていても、歯周病が進みやすい人とそうでない人がいるのはなぜでしょうか?
それは、細菌の量や種類だけでなく、「体の抵抗力」や「環境要因」が深く関わっているためです。
たとえば、免疫力の低下、ストレス、睡眠不足、喫煙、糖尿病などがあると、体の防御反応がうまく働かず、炎症が長引きやすくなります。また、生活リズムの乱れや栄養不足も、歯周組織の修復を妨げる要因です。
つまり歯周病は「細菌の問題」だけでなく、体と生活環境のバランスが崩れることで進行しやすくなる病気なのです。
歯周病の重症度と進行リスク(Stage/Grade)
歯周病は、その進行度と進行スピードによって「Stage(ステージ)」と「Grade(グレード)」で評価されます。
Stageは歯周病の重症度を示し、歯を支える骨の破壊量や歯の動揺の程度で判定します。初期(StageⅠ)から重度(StageⅣ)まで段階的に分かれ、治療の難易度も異なります。
一方、Gradeは進行リスク(速度)を表し、主に喫煙や糖尿病の有無が大きく影響します。喫煙者や血糖コントロールが不安定な人は、同じStageでも進行しやすい傾向があるため注意が必要です。
歯科医院では、歯周ポケットの深さ、出血、骨吸収の有無などを精密に測定し、一人ひとりのリスクを見極めた治療計画を立てます。
歯周病になりやすい人の特徴チェック

歯周病の発症や進行には、生活習慣や体質、全身の健康状態が深く関係しています。ここでは、歯周病になりやすい人の特徴を具体的に見ていきましょう。喫煙や糖尿病といった全身的な因子から、口呼吸や歯ぎしりなどの局所的な要因まで、複数のリスクが重なるほど進行スピードは速くなります。
自分に当てはまる項目がある場合は、早めの受診とプロフェッショナルケアでコントロールすることが大切です。ここから、代表的なリスク因子を一つずつ解説します。
喫煙者(電子タバコ含む)は炎症が治りにくい
喫煙は、歯周病の最も強力なリスク因子のひとつです。たばこの煙に含まれるニコチンや一酸化炭素が歯ぐきの血流を悪化させ、免疫機能を低下させるため、炎症が治りにくくなります。
その結果、出血や腫れといった初期症状が目立ちにくく、気づかないうちに歯を支える骨が失われるケースも少なくありません。電子タバコでも、加熱成分による血管収縮作用が報告されています。
禁煙によって歯ぐきの血流が改善し、治療効果が高まることが多いため、受診時には喫煙状況を必ず伝えるようにしましょう。
糖尿病がある/血糖コントロールが不安定
糖尿病のある方は、血糖値が高い状態が続くことで免疫機能が低下し、細菌に対する防御力が弱まるため、歯周病が進行しやすくなります。また、炎症が長引くことで血糖値のコントロールがさらに悪化するという悪循環が起こることもあります。
近年の研究では、歯周病治療を行うことでHbA1c(血糖指標)が改善するケースも報告されています。つまり、歯周病と糖尿病は相互に影響し合う関係なのです。
患者様のかかりつけの内科と情報共有を行いながら治療を進めることで、お口と全身を一体的に管理することが重要です。
口呼吸・お口の乾燥(ドライマウス)
口呼吸やドライマウスの人は、唾液の抗菌作用・自浄作用が低下するため、歯周病菌が繁殖しやすい環境になります。唾液は細菌の活動を抑え、歯ぐきを守る大切なバリアですが、口を開けて呼吸する習慣があると乾燥してその機能が失われます。
とくに就寝中の口の乾き・いびき・朝のネバつきは、口呼吸のサインかもしれません。鼻づまりや歯並び、姿勢などが関係していることもあるため、必要に応じて耳鼻科との連携や鼻呼吸トレーニングを行うことが有効です。
お口の乾燥を感じたら、早めの相談で原因を見極め、歯周病の進行を防ぎましょう。
口呼吸が歯周組織に及ぼす具体的影響
口呼吸が続くと、常に空気が流れる上顎前歯や臼歯の歯ぐきが乾燥して炎症を起こしやすくなります。特に頬側の歯ぐきは唾液の保護が届きにくく、赤く腫れたり出血しやすくなることがあります。
また、口呼吸による筋肉バランスの変化で、歯の位置や咬み合わせにも影響が出る場合があります。改善には、鼻呼吸の練習や、舌の位置を整える口腔筋機能療法(MFT)などが有効です。
こうした機能的な要因を見逃さず、歯ぐきの炎症とあわせて原因から整える治療が重要です。
歯ぎしり・食いしばり(咬合性外傷)
歯ぎしりや食いしばりのクセがある人は、歯に過度な力(咬合力)が集中しやすく、炎症を起こした歯ぐきや骨にダメージを与えてしまいます。特に夜間は無意識に力が加わるため、歯周病が進行している部分では骨の吸収や歯の動揺が早まることがあります。
歯科では、歯ぐきや歯の動きを観察し、必要に応じてナイトガード(マウスピース)で力を分散させる方法を提案します。また、噛み合わせの高さや歯列のバランスを整える「咬合調整」も有効です。
「朝起きると顎が疲れている」「歯が欠けやすい」と感じる方は、早めのチェックが歯の寿命を守ります。
歯並び・詰め物の段差など清掃性の悪化
歯並びの乱れや詰め物・被せ物の段差があると、歯ブラシの毛先が届きにくく、プラークが溜まりやすい環境になります。特に歯と歯の間や歯ぐきの境目は、見た目ではきれいでも細菌が潜みやすい場所です。
このような部位は「プラークリテンションファクター(汚れのたまり場)」と呼ばれ、歯周病の温床となることがあります。歯列矯正で歯並びを整えたり、不適合な詰め物を調整・再製することで、清掃性を改善し炎症を予防できます。
ヤスデンタルクリニックでは、咬合や補綴の精密チェックを通じて、見た目と清掃性の両立を目指した治療を行っています。
歯並び・詰め物の段差など清掃性の悪化
歯並びの乱れや、古くなった詰め物・被せ物の段差は、歯ブラシが届きにくくプラークが溜まりやすい原因になります。特に歯と歯の間や歯ぐきとの境目に汚れが残ると、炎症が起こりやすく、歯周病のリスクが高まります。
清掃しやすいお口をつくるには、矯正治療や補綴(詰め物・被せ物)の見直しが効果的です。ヤスデンタルクリニックでは、咬み合わせや歯ぐきとの境界を考慮しながら、見た目と機能を両立するセラミック修復を行っています。
「昔のセラミックをきれいにやり直したい」「自然な歯並びに整えたい」という方には、精密なセラミック矯正による再治療も可能です。
女性ホルモンの変動(妊娠・思春期・更年期)
女性はホルモンの変化によって、歯周病のリスクが高まる時期があります。思春期・妊娠期・更年期には、女性ホルモン(エストロゲンやプロゲステロン)が変動し、歯ぐきの中で特定の細菌が増えやすくなることが知られています。
その結果、プラーク量が少なくても歯ぐきが腫れたり出血しやすくなることがあります。特に妊娠中はホルモン変化に加えて、つわりや食習慣の変化でブラッシングが難しくなるため、注意が必要です。
妊娠中の口腔ケアのポイント
妊娠中はホルモンバランスの変化によって、歯ぐきの炎症(妊娠性歯肉炎)が起こりやすくなります。特に妊娠中期には歯ぐきが敏感になり、わずかなプラークでも腫れや出血が起こることがあります。
つわりで歯みがきがつらい時期は、無理せずうがい中心でもOK。体調が安定する妊娠中期に、歯科でのクリーニングやブラッシング指導を受けるのがおすすめです。
ストレス・睡眠不足・食生活の乱れ
ストレスや睡眠不足は、自律神経やホルモンバランスを乱し、免疫力の低下を招きます。その結果、歯周病菌への抵抗力が弱まり、歯ぐきの炎症が悪化しやすくなります。また、ストレスによって食いしばりが強くなると、歯や歯ぐきへの負担も増加します。
さらに、食生活の乱れも歯周病の進行に影響します。甘い飲み物や間食の頻度が多いと、プラークが蓄積しやすくなり、夜遅い食事は唾液量の減少で細菌が増えやすくなります。
まずは、十分な睡眠と規則正しい食事、ストレスケアを意識することが、歯ぐきを守る第一歩です。
家族に重度歯周病の方がいる(遺伝要因)
歯周病そのものが遺伝するわけではありませんが、免疫反応のタイプや唾液の性質、骨の代謝傾向など、歯周病に「なりやすい体質」が遺伝的に受け継がれることがあります。
また、家族内では食習慣やブラッシング習慣、喫煙などの生活環境も似ているため、同じようなリスクを抱えている場合が多いのです。特に親が若いころから歯周病で歯を失っている場合は、早期のチェックと定期的なクリーニングを強くおすすめします。
歯ぐきの健康を守るには、「遺伝だから仕方ない」と諦めず、自分のリスクを把握して予防に取り組むことが何より大切です。
歯周病になりやすい人のセルフチェック

自分が歯周病になりやすいタイプかどうか、簡単なセルフチェックで確認してみましょう。次の10項目のうち、当てはまるものが多いほどリスクが高いと考えられます。
-
歯ぐきから出血することがある
-
朝起きたときに口の中がネバつく
-
口臭が気になる
-
歯が長く見える、歯ぐきが下がった気がする
-
喫煙している(または過去にしていた)
-
糖尿病がある、または血糖が高めと言われた
-
ストレスが多く、睡眠不足気味
-
歯ぎしりや食いしばりを指摘された
-
口呼吸やいびきをかくことがある
-
家族に歯周病で歯を失った人がいる
気になる症状がある方は、自己判断せず、早めの受診で現状を確認しましょう。
今日からできる予防習慣とメインテナンス計画

歯周病の予防は、毎日のセルフケアと定期的なプロフェッショナルケアの2本柱で成り立ちます。どちらか一方だけでは不十分で、双方を組み合わせて行うことで、炎症の再発を防ぎ、健康な歯ぐきを維持できます。
まずは、自分の磨き残しやすい部分を把握し、歯ブラシの動かし方や道具を見直すことが大切です。さらに、歯科医院でのスケーリングやPMTC(専門的クリーニング)を定期的に受けることで、家庭で落とせないバイオフィルムを除去できます。
禁煙や食生活の改善、ストレスケアなどの生活習慣の見直しも、歯周病予防の効果を高める重要なポイントです。
毎日のセルフケア(部位別の磨き分け)
歯周病予防の基本は、毎日の正しいブラッシングです。ただ「磨く」だけではなく、どの部分に汚れが残りやすいかを意識することが大切です。
特に注意したいのは、歯と歯ぐきの境目・歯の裏側・奥歯の奥(遠心)です。ここにはプラークが残りやすく、歯周病の発症ポイントになりやすい場所です。歯間ブラシやデンタルフロスを使って、歯と歯の間の汚れもていねいに落としましょう。
ヤスデンタルクリニックでは、患者さんごとのリスクに合わせた磨き方の指導やケアグッズの選定を行っています。自分に合った方法を身につけることが、長期的な予防の第一歩です。
プロフェッショナルケア(スケーリング/PMTC)
毎日のブラッシングで落としきれないのが、歯石やバイオフィルム(細菌膜)です。これらは歯科医院での専用器具による除去が必要になります。スケーリングでは歯石を丁寧に取り除き、PMTCでは歯の表面を磨いて細菌の再付着を防ぎます。
これらの処置は、歯ぐきの健康を保ち、再発を防ぐための「メインテナンス治療」の一部です。痛みに配慮したクリーニングを行うことで、快適に通院を続けることができます。
通院間隔はリスクに応じて3〜6か月ごとが目安。症状が安定していても、定期的に専門的ケアを受けることで、歯を長く守ることが可能です。
禁煙と血糖コントロールの両輪
歯周病を効果的に予防・改善するには、禁煙と血糖コントロールの両立が欠かせません。喫煙による血流低下は、歯ぐきの炎症を悪化させるだけでなく、治療後の回復を遅らせます。一方で、高血糖状態は免疫力を下げ、細菌感染を助長するため、炎症を長引かせます。
禁煙によって歯ぐきの血行が改善し、歯周治療の効果が高まることが報告されています。また、歯周治療によって血糖値(HbA1c)が改善するケースもあり、全身管理の一環として重要です。
歯科と内科が連携し、生活習慣をトータルで整えることが、お口と体の健康を守る最短ルートとなります。